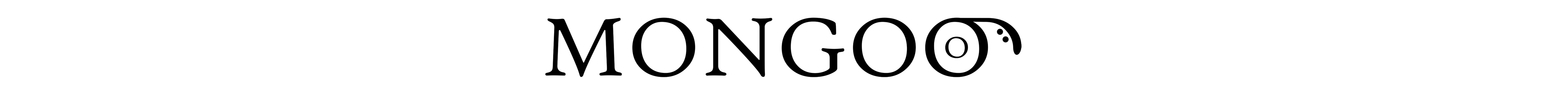2025/11/09 07:55
前編ではAI生成をめぐる混乱が
かつての「デジカメ不可」や「Photoshop禁止」と同じ構造にあることを書いた。
後編はその延長としてフォトコンテストの信頼をどう保つかについて。

技術はあるけど理解は届かない
AIによる画像生成が一般化し
真正性を保証するための技術的仕組みはすでに存在している。
それらは報道関係で主にすでに使われている。
それらは報道関係で主にすでに使われている。
ほかにブロックチェーンを使った認証や
画像データの改ざん検知システムなどある。
でも、それを活かす前提に知識と理解が必要になる。
たとえば、ブロックチェーン上の取引を確認するための代表的なサービスに
Etherscan(イーサスキャン)がある。
しかし、それを気になった時に能動的に使える人はどれほどいるだろうか。
技術が存在することと運用できることのあいだには距離がある。

8割が理解できる解としてRAWデータの提出
そのような状況の中で現実的な解として挙げたいのがRAWデータの提出。
RAWファイルには撮影時の情報がそのまま残り次のような意味を持つ。
・撮影されたという証拠
・編集や合成を可視化
・提出を条件にすることで生まれる一定の抑止力
もちろん、RAW提出だけですべての不正を防げるわけではない。
それでも現時点で多くの人が理解し共有可能なラインになる。
審査の透明性
技術による裏づけと同じくらい大切なのが、審査の視点を明らかにすること。
どんな基準で作品を選び何を評価したのか。
その説明があるだけで鑑賞者の推測とのずれは小さくなる。
作品の受け止め方が共有されれば誤解や疑念も減る。
その点、木村伊兵衛賞は示唆的だ。
賞の発表とともに数ページに渡る選考理由が掲載される。
時代表現の最先端を評価しながらも選評の中には納得がある。
時代表現の最先端を評価しながらも選評の中には納得がある。
どのような視点で作品を見たのかが言葉として残されることで
写真文化そのものへの信頼が生まれている。
コンテスト運営に求められる姿勢
AI時代のフォトコンテストに必要なのは透明性と明文化。
・応募要項で「編集・AI使用の可否」を明確にする
・RAWデータ提出を義務化
・「AI補助(ノイズ除去・補正)」と「生成・合成」の線引きを定義する
・審査の選評理由を公開する
こうした取り組みは制限ではなく写真という共有の場を保つための仕組み。
文化を支えるために、まず信頼の共通言語を持つ必要がある。
揺れの中で写真は生きている
RAWの提出は自分が確かにこの瞬間を撮ったと示す。
そこに写真の生がある。
そして、テクノロジーが進化するたびに新しい揺れが生まれる。
どこまでが写真か?
その揺れの中で写真表現は形を変えながらも続いていく。
信頼を築こうとする努力そのものが、
この時代の撮るという行為の一部になっている。
この不安定さこそが写真という表現の面白さでもある。
🔸本革 GRⅢ・GRⅢx 対応カメラポーチ(ハンドストラップ付き)