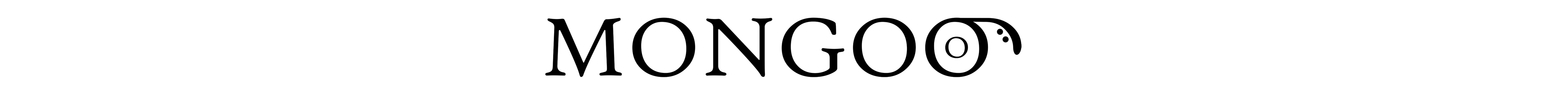2025/11/07 12:32
AI生成写真をめぐる議論は、かつてのデジカメ不可やPhotoshop禁止と同じ構造を持つ。
技術が進化するたびに写真とは何か?と問われてきた。

フォトコンテストで「受賞作品がAI生成だったのでは?」という議論が起きている。
きっかけとなったのはグランプリを受賞したルリビタキの写真。
あまりにアップであり、あまりに高精細で羽の一本一本まで解像している。
ルリビタキは肉眼では追えないほど高速で飛ぶ鳥だ。
その動きをこれほどまでに鮮明に捉えた一枚には
「どんな超望遠レンズ?どんなシャッタースピードで撮った?」といった
撮影条件を想像するコメントが集まった。
その完璧さゆえに「本当に撮られたものなのか」という疑問が生まれている。
AIによる画像生成技術が進化し、いまや実写と見分けがつかない。
写真と技術は、常にせめぎ合ってきた
AIをめぐる混乱は新しい話ではない。
写真はこれまでも技術の変化に揺れながら進化してきた。
デジタルカメラが登場した当初、一部のフォトコンテストで
「デジカメで撮影した作品は応募不可」と明記されていた。
デジカメは写真ではないとする時代があったのだ。
さらにその後「フォトショップによる加工は禁止」というルールも加わった。
色調補正やトリミングですら写真の純度を損なうと見なされた。
それは新しい技術に対する戸惑いだった。
フィルムからデジタルへ、そしてAIへ。
技術が変わるたびに写真の定義が揺れていた。
テクノロジーが進化するたびに「撮る」という定義が揺れる
いつの時代もテクノロジーは先を行き、社会はその意味を後から理解してきた。
デジカメもフォトショップも当初は邪道とされながら
いまでは写真文化を支える基盤となっている。
AI生成をめぐる混乱も同じ構造にある。
技術が進化するたびに「撮る」とは何かが問われる。
追いつこうとする中でそもそも「写真とは何か」という問いが生まれる。
この揺れこそが写真表現の面白さでもある。
後編はこれから審査の信頼性をどう守るか。
RAWデータ提出とルールづくりについて。
>> フォトコンテストとAI生成写真【後編】|RAWデータ提出と信頼のルール
🔸本革 GRⅢ・GRⅢx 対応カメラポーチ(ハンドストラップ付き)