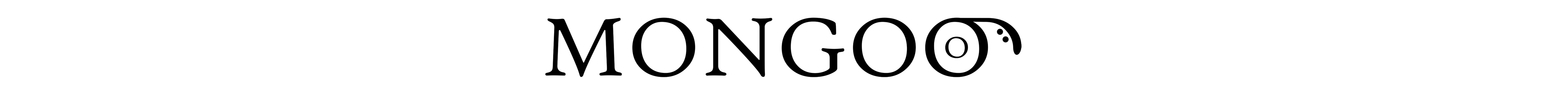2025/10/07 12:59
この記事を読んで、もしかしたら少しモヤっとする人もいるかもしれません。
これは、あくまで私自身の整理として書いています。
分かりやすい写真 がある一方で、
分からない写真 というものもあります。
そして私は「分からない写真」のほうに
心を惹かれるようになりました。
※ 写真:2010年・2013年・2016年・2021年の個展より

私の体験から
私はもともと、風景写真を撮っていました。
2000年代、写真雑誌をめくるたびに
「こんな場所があるのか!」と驚かされ、
その世界に強く惹かれていきました。
やがて興味が勝り、会社員を辞め
風景写真に本格的に向き合うために裏磐梯へ移住しました。
その頃、フジフイルムフォトサロンの個展公募に通って初めて個展を開催。
それをきっかけに、風景写真家を名乗るようになりました。
その頃に撮っていたのは、今で言う「映える写真」
光の条件、構図、季節感、それらを読みながら撮ることに夢中でした。
メインカメラは PENTAX の中判カメラ。
フィルムは ベルビア50。
デジタルカメラも使っていましたが、
結局フィルムしか使わなくなりました。
便利で効率的なものが必ずしも良いとは限らない。
当時はそのことを
不思議に感じながら受け入れていた気がします。
フィルムは節約しながらが基本で、
1日に1本も撮らない日もあれば、10本使う日もある。
対象が自然である以上、
その瞬間とそのタイミングが何に繋がるか、何を見だせるかというひっかかりがすべてでした。
今ではポジフィルムが1本4,000〜5,000円、現像料も1,500円以上。
当時はフィルム500円、現像600円ほどだったと思います。
振り返れば、本当に貴重な体験でした。
そして今はやりたいときにやったもの勝ちだと
あらためて思います。
幸運なことに当時、旅行会社と業務提携できて、
風景写真に関わるスキルや経験は仕事としても生かせました。
だから映える写真を否定する気持ちはありません。
それは多くの人に旅の魅力を伝えるための大切な手段でした。
しかしSNSとデジタルカメラの波が押し寄せる中で、
当初感じていた神秘性が薄れていくのを感じました。
誰でも簡単にキレイを再現できる。
これで終わった気がしたのです。
これからの風景写真を考えていました。

仏教の説法と「伝わる」ということ
ある僧侶が話していた言葉が、ずっと印象に残っています。
「本当に学びになるものは、すぐには伝わらない」
それはその場で分かった気になる話よりも、
時間をかけてあとで腑に落ちる話のほうが価値があるということ。
分かるというのは、
聞き手の中にすでにある常識や経験を掘り起こしているだけ。
つまり、新しい認知は起きていません。
「分かる = 自分のなかで処理できる」ということ。

映える写真の限界
僧侶のお話は写真にもよく似ています。
分かる写真は、見る人の中にある常識や経験に接続する。
それは心地よく、誰もを納得させる快さを持っています。
でも、その快さの中では、
見る人も撮る人も、もう成長できない。
分かる写真は安全で、整っていて、綺麗で
「説明のいらない」写真。
けれど、そこには未知への扉がありません。
分かる写真は、
成長を止めるものではなく、成長が一段落した地点を示しているのかもしれません。
そして、そこから「もう一歩先がある」と気づいたときこそ、成長のはじまり。

快さの中にある限界を感じたとき、
私は「分からない写真」へと興味を持ちはじめました。
後編、分からない写真は、理解の外にある世界を思い出させる。
未知に触れることで感性が更新されていくことについて書いてみたいと思います。
🔸本革 GRⅢ・GRⅢx・GRⅣ 対応カメラポーチ(ハンドストラップ付き)
ハンドメイドにつき不定期販売となります。